凪司工房の徒然
お知らせ・小説・ツイノベ・随筆・エッセイなど
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
Ren'Py はじめます。 の補講 第6.5回
凪 「Ren'Pyはじめます。 の補講 第6.5回です」
「こちらでは本編では悠長に触れていられない、Ren'Py のプログラム的な話や、やや突っ込んだ内容についての講義であったり、また参照記事であったりを書いていきます」
「今回は第6回の補足です」
「少し間が開きましたが、更新できる範囲で気長にやっていきますので、宜しくお願いします」
「という訳で、補講を読まれる方は ↓続きの記事からお願いします」
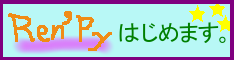
「第6回では音楽について簡単な説明をしました」
「背景音楽(BGM)を鳴らすか、効果音(SE)を鳴らすかの命令の違いは、それがループするかしないか、というものでしたね」
「音楽については画像よりはずっと簡単です」
「ただ音声ファイルは画像ファイルよりも形式が多くて、そもそもそれらを製作するのに使うツールが膨大にあって、フリーでも結構いいソフトシンセやDAWであったりが揃っている現在では、どの形式でなければいけない、という縛りは特に無いように思います」
「今回はそんなプログラム面以外のお話もここでしたいと思います」
6.1 <音声ファイルの形式>
「みなさんは普段パソコンなどで音楽を聴いたりしますか?」
「最近は動画サイトとかで聴いたりする人も多いんでしょうかね」
「携帯プレイヤーを使う人には mp3とかが馴染みがいいでしょうか」
「現在パソコンやゲームなんかで使われているものでは次のような種類があります」
「このうちRen'Pyで使えるのは WAV、MP3、OGG Vorvisの3つです」
「ただMP3は違法ファイルの疑いがあったり、特許権を主張する研究所があったりで、自分で楽しむ以外のもの、たとえば不特定の他人に配布するような、ゲームのような作品の場合には使わないことが推奨されています」
「なので、一応使用することは出来ますが、できれば WAV や OGG Vorvis といった形式を利用しましょう」
「ここでは音声ファイルの形式変換については扱いませんが、検索すると簡単に変換できるソフトなどの紹介がありますので、そちらを参照して、自分なりに使いやすそうなソフトを見つけて下さい」
(ちなみに私は Audacity というフリーソフトを使って変換することが多いです)
6.2 <フェードイン/アウト>
「本編では扱いませんでしたが(時間が不足していたので)、音楽をいれる際にフェードインやフェードアウトの効果をつけたいことがあると思います」
「もちろんRen'Pyではそれらが簡単に行えるようになっています」
「音声ファイルを指定した後に fadein 秒数 をつけるだけです」
「フェードアウトの場合は、音楽を止める命令を入れてから……」
「のようにします」
6.3 <音楽をつなげる>
「音声ファイルは1つだけでなく、2つ以上指定することができます」
「[] を使ってその間に並べることで、続けて演奏してくれます」
「BGMで利用することは少ないでしょうが、SEの場合なんかは使う場面もあるかと思います」
6.4 <特殊な命令>
「本編では紹介しませんでしたが、queue という命令があります」
「これは play の代わりに使うのですが、実際に使ってみるとどこがどう違うのか? と思われるかも知れません」
「この queue 命令は、あらかじめ音声ファイルを読み込んでから演奏してくれる、というものです」
「play と queue で聞き比べると分かると思うのですが、play の場合だと若干のタイムラグがあってから演奏が始まります」
「それは play の場合はそこに移った時点で音声ファイルを読み込むからです」
「短いものの場合はそれほど気になりませんが、大きな音声ファイルであったり、タイミングが重要な場面での音の扱いである場合、その僅かなタイムラグが気になる場面があると思います」
「そういった場合には play ではなく queue を使いましょう」
「音関連では他にもアドベンチャー系ゲームなら”声”という重要な要素がありますが、今回はそれは扱いません」
(大規模なものの製作は今のところ考えてませんので、声つきのゲーム製作についての勉強は後回しにする予定にしております)
「音量であったり、PANを操作したりもできるのですが、今までとは異なる命令文の形が出てきますので、また別の機会にそれも回します」
「基本的なことは今回紹介したもので出来ると思いますので、基礎編ということでご了承下さい」
「それではまた本編で」
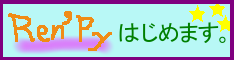
「の補講 第6.5回」
「第6回 -俺の鼓動が聴こえるか?-」
「の補講 第5.5回」
「第5回 -君に会いに行く-」
「第4回 -魔女の誘惑-」
「の補講 第3.5回」
「第3回 -出会いと別れ-」
「の補講 第2.5回」
「第2回 -そんな話は聞いてない-」
「の補講 第1.5回」
「第1回 -魔王現る-」
「第0回 -1人の敗者-」
「こちらでは本編では悠長に触れていられない、Ren'Py のプログラム的な話や、やや突っ込んだ内容についての講義であったり、また参照記事であったりを書いていきます」
「今回は第6回の補足です」
「少し間が開きましたが、更新できる範囲で気長にやっていきますので、宜しくお願いします」
「という訳で、補講を読まれる方は ↓続きの記事からお願いします」
「第6回では音楽について簡単な説明をしました」
「背景音楽(BGM)を鳴らすか、効果音(SE)を鳴らすかの命令の違いは、それがループするかしないか、というものでしたね」
「音楽については画像よりはずっと簡単です」
「ただ音声ファイルは画像ファイルよりも形式が多くて、そもそもそれらを製作するのに使うツールが膨大にあって、フリーでも結構いいソフトシンセやDAWであったりが揃っている現在では、どの形式でなければいけない、という縛りは特に無いように思います」
「今回はそんなプログラム面以外のお話もここでしたいと思います」
6.1 <音声ファイルの形式>
「みなさんは普段パソコンなどで音楽を聴いたりしますか?」
「最近は動画サイトとかで聴いたりする人も多いんでしょうかね」
「携帯プレイヤーを使う人には mp3とかが馴染みがいいでしょうか」
「現在パソコンやゲームなんかで使われているものでは次のような種類があります」
・WAV (ウェーブ) ……大半は無圧縮の音声データ。扱いやすさが特徴
・MIDI(ミディ) ……音のデータではなく演奏データのみが書かれている。パソコンにより音色は異なる。
・WMA(ウインドウズメディアオーディオ) ……Windowsを使う人にはお馴染みの形式。
・MP3(エムピースリー) ……容量を軽くできることから普及した圧縮形式。
・OGG Vorvis(オッグ・ボルビス) ……MP3が特許や著作権問題がある為、登場した新しい圧縮形式。
・ACC(エーエーシー) ……動画などでよく使われる音声圧縮方式。MP3の後継。
「このうちRen'Pyで使えるのは WAV、MP3、OGG Vorvisの3つです」
「ただMP3は違法ファイルの疑いがあったり、特許権を主張する研究所があったりで、自分で楽しむ以外のもの、たとえば不特定の他人に配布するような、ゲームのような作品の場合には使わないことが推奨されています」
「なので、一応使用することは出来ますが、できれば WAV や OGG Vorvis といった形式を利用しましょう」
「ここでは音声ファイルの形式変換については扱いませんが、検索すると簡単に変換できるソフトなどの紹介がありますので、そちらを参照して、自分なりに使いやすそうなソフトを見つけて下さい」
(ちなみに私は Audacity というフリーソフトを使って変換することが多いです)
6.2 <フェードイン/アウト>
「本編では扱いませんでしたが(時間が不足していたので)、音楽をいれる際にフェードインやフェードアウトの効果をつけたいことがあると思います」
「もちろんRen'Pyではそれらが簡単に行えるようになっています」
play music "音声.ogg" fadein 1.0
「音声ファイルを指定した後に fadein 秒数 をつけるだけです」
「フェードアウトの場合は、音楽を止める命令を入れてから……」
stop music fadeout 1.0
「のようにします」
6.3 <音楽をつなげる>
「音声ファイルは1つだけでなく、2つ以上指定することができます」
play music [ "音声01.ogg", "音声02.ogg", "音声03.wav" ]
「[] を使ってその間に並べることで、続けて演奏してくれます」
「BGMで利用することは少ないでしょうが、SEの場合なんかは使う場面もあるかと思います」
6.4 <特殊な命令>
「本編では紹介しませんでしたが、queue という命令があります」
「これは play の代わりに使うのですが、実際に使ってみるとどこがどう違うのか? と思われるかも知れません」
「この queue 命令は、あらかじめ音声ファイルを読み込んでから演奏してくれる、というものです」
「play と queue で聞き比べると分かると思うのですが、play の場合だと若干のタイムラグがあってから演奏が始まります」
「それは play の場合はそこに移った時点で音声ファイルを読み込むからです」
「短いものの場合はそれほど気になりませんが、大きな音声ファイルであったり、タイミングが重要な場面での音の扱いである場合、その僅かなタイムラグが気になる場面があると思います」
「そういった場合には play ではなく queue を使いましょう」
「音関連では他にもアドベンチャー系ゲームなら”声”という重要な要素がありますが、今回はそれは扱いません」
(大規模なものの製作は今のところ考えてませんので、声つきのゲーム製作についての勉強は後回しにする予定にしております)
「音量であったり、PANを操作したりもできるのですが、今までとは異なる命令文の形が出てきますので、また別の機会にそれも回します」
「基本的なことは今回紹介したもので出来ると思いますので、基礎編ということでご了承下さい」
「それではまた本編で」
「の補講 第6.5回」
「第6回 -俺の鼓動が聴こえるか?-」
「の補講 第5.5回」
「第5回 -君に会いに行く-」
「第4回 -魔女の誘惑-」
「の補講 第3.5回」
「第3回 -出会いと別れ-」
「の補講 第2.5回」
「第2回 -そんな話は聞いてない-」
「の補講 第1.5回」
「第1回 -魔王現る-」
「第0回 -1人の敗者-」
PR

